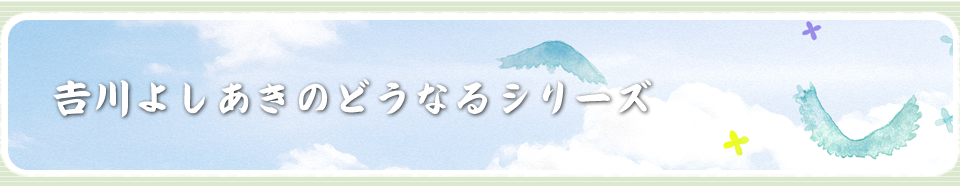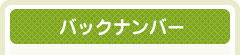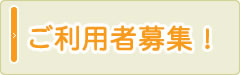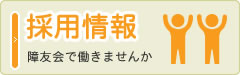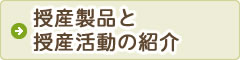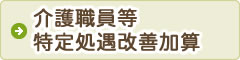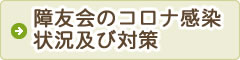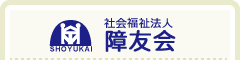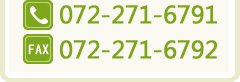どうなるこの国の障害者福祉
本当にどうなってゆくのか、わが国の社会福祉!
平成27年度がスタートしました。わが国の障害者福祉にとっては今年度も又波乱含みの予感です。
すでに年度当初から実施されはじめたこと、そして、次年度からの施行にむけて今年度中に準備されることなど、今号では主要なそれぞれの法制度をとりあげ、その課題などについて考えます。
この国の社会福祉が、そして障害者福祉がどんな顔になってどちらの方向にむかわされようとしているのか、うかうかとはすごせない平成27年度になりそうです。
- 子ども・子育て新制度の施行に伴い保育所の利用システムが名実ともに「契約利用型」に変更されました。
平成12年度からの高齢者福祉(介護保険制度)、15年度からの障害者福祉(支援費制度)に続いていよいよ児童福祉(保育所制度)も事実上「契約利用型」の社会福祉制度になりました。児童養護施設、児童自立支援施設、養護老人ホームなど各種の社会福祉施設の一部には「措置制度」が残された(契約利用にはなじまない分野)ものの、ほぼ全ての社会福祉施設領域から「措置制度」は消滅したといって過言でありません。
平成12年以来いつかくる日、であったこのとき。約15年の歳月を費やして、一応は「完結」の気配です。はたして、かねて国が求めてやまなかった「社会福祉の基礎構造改革」はこれで幕引きとなるのでしょうか。それとも…
社会福祉の「契約利用」を否定するものではありません。しかし、このシステムには大きな陥穽が潜んでいると言わざるを得ません。
社会福祉の利用にあたって、国民一人ひとりの自主的で主体的な制度選択や決定の保障、という点では確かに前向きな仕組みです。しかし、その反面、それだけの「自己責任」を求められます。そして、制度運用の如何によっては社会福祉の実施にかかる公的責任の軽減、利用者の自己責任の増大につながります。
又、国民の、低所得を理由とする利用の自己抑制(いわゆる利用控え)をひきおこします。その上、制度の利用意向が直接的には行政に届かない(利用について行政が直接関与しなくなるため)こともあって、行政は本当のニーズの質量を的確に把握できない(しない)という事態をもまねきかねません。当然それは予算措置にも反映されます。
今後、すでに実施されている契約利用型社会福祉制度をも含めて、公の費用のかけ方、その責任のあらわし方など、契約利用システムの負の側面、懸念される点については一層注意深く見つめ続けてゆく必要があります。
- 介護報酬や障害福祉サービス事業報酬が改訂されました。
政府の3年毎の報酬見直しの結果、今年度、高齢者介護事業所への報酬が大きく減額されました(平均約2.27%の減額)。障害者福祉関係についても同様で、基本報酬は軒なみ減、各種の加算によってかろうじて(±0)。実質的にはマイナス改訂と言わざるをえない状況です。
生活保護基準も切り下げられました。この国の社会保障、社会福祉予算の圧縮方針が各法制度に確実に反映された形です。福祉人材の確保が大変厳しい、など、事業運営(経営)全般の課題が山積する中、このような国家予算の編成方針ははたしてどのような結果をもたらすでしょう。大きな危惧を抱かざるをえません。
『今の予算編成では、裁量的経費は1割カットの予算要求が求められている。義務的経費である社会保障費は自然増分の要求は認められている。このような制度が必要だといった政策的増のケースの財源は、その関連予算の中から削って捻出するのが基本になっている。ワーキンググループで議論していただく項目のほとんどは予算増につながるものであり、効率化できるところはないか、ということも論点としてあげていただけるのであればありがたい』。(平成27年3月17日に開催された厚労省の社会障審議会障害者部会「障害福祉サービスの在り方等に関する論点整理のためのワーキンググループ」の会合時にあった、厚労者保健福祉部長の発言―全国社会就労センター協議会、セルプ通信連報№467、2015.3.20から引用)。
益々深刻化するわが国の少子高齢化。増大する一途のニーズ。しかしそれに対応できない国の財政(源)状況。減額予算の背景、事情はきわめて明白です。とはいえ、このような対応が施策の柱であってよいはずがありません。今こそ、まずは何を大切にしなければならないのか、そしてそのための予算編成の考え方は、優先順位も含めてどのようにあらねばならないのか、など、この国の先き行きをみすえた大きな視座が求められると言えます。
- 社会福祉法人制度改革がはじまります。
「多額の内部留保金」を、しかも「無目的にため込んでいる」。「理事長が法人を私物化し、業者と不適切な取り引きが日常化している」。はては「法人の売買にまで及んでいる」など、マスコミ、メディアの特集報道を発端にわが国の社会福祉法人は諸方からの厳しい批難にさらされました。少なくとも国はそのように喧伝しています。
先般、平成27年2月12日、社会福祉法人制度の改革方針とその方向性(改革案)が国の検討会(厚労省の社会保障審議会福祉部会)によってとりまとめられ発表されました。
示されたな改革案は相当な規模で広範囲に及びます。しかも制度の根幹にまでふみ込んでいて抜本的ですらあります。
この改革案は実定法である社会福祉法の改正案として現在開会中の通常国会に提出される予定です。そして国会決議を経て来年度、28年度から順次施行されるはこびです。改革案自体は私にとっては決して不快なものではありません。久しく問題視されてきた既存の社会福祉法人のマイナス面、その実態や背景、原因などがそれなりに指摘されている、と思われるからです。又、公金(税金)を使用して、公の責務を代替実施する社会福祉法人の本来のあるべき姿を厳しく問うてもいるからです。具体の手続き上現実的ではない、と考えられる改革案も散見されますが、大方についてはほぼ肯定できるものです。
ただし、社会福祉法人の「非課税」扱いや公的補助金に関する表現や評価には強い違和感をおぼえます。そして、その具体策として提案される「社会福祉施設職員等の退職手当共済制度の見直し案(掛け金への公的助成の廃止)」については全く容認できるものではありません。社会福祉の実施に関する国と社会福社法人との関係性―事業実施の委託と受託の相互関係―社会福祉法人における公的責務の代替性、最終的な国の責任性などを国自らが否定し放棄することにほかならないからです。
社会福祉法人制度がどのように「改革」されようとも、わが国の社会福祉の実施責任はあくまでも公―国にあるということ、この原則だけは決して忘れないでおきたいと思います。
- 障害者総合支援法、3年目の見直し作業が本格化します。
「装いもあらたに(?)」平成25年度からスタートした障害者総合支援法。27年度は施行後3年目に当たります。法律の附則に示された「施行後3年後の見直し規定」を根拠としていよいよ見直し作業が始まる予定です。
昨年度末までに、すでに何回かのワーキンググループの会合が開催されています。ワーキンググループとは「障害者福祉サービスの在り方等に関する論点整理のためのワーキンググループ」と称して、厚労省の「社会福祉審議会障害者部会」のもとに設置された組織です。本格的な見直し作業の前さばき的な役割を担っています。
これまでの会合で見直し規定の論点案となる「今後議論を深めるべき事項(案)」がとりまとめられ、今般公表されました。以下、紙面の関係で大項目のみを列記します。
- 常時介護を要する障害者等に対する支援のあり方
- 手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援のあり方
- 高齢の障害者に対する支援のあり方
- 障害者等の移動の支援のあり方
- 障害者の意思決定支援・成年後見制度の利用促進のあり方
- 障害支援区分の認定を含めた支給決定のあり方
- 障害者の就労支援のあり方
- 精神障害者に対する支援のあり方
- 障害児支援のあり方
- その他の障害福祉サービスのあり方
中項目にはより具体的な文言によって合計30の論点、課題に整理され提起されています。
27年度中にはそれぞれ細部にわたる「あり方」が示される予定です。
はたして、各課題がどのように見直され、そして28年度以降の施策に反映されるでしょうか。ぜひとも前むきな議論と政策提起を期待するものです。が、しかし、一層深刻化する国の財政状況や予算の編成方針(先述の厚労省保健福祉部長の談)のもとでは全く楽観できません。今後、その都度公表されるであろう議論の行方を注目してゆかねばなりません。
- 「障害者差別解消法」の施行にむけての諸準備が具体化されます。
障害当事者や家族、関係者たちが切望してやまなかった「障害者差別解消法」が平成26年6月に成立し、来年度、28年度からようやく施行のはこびとなりました。
本法は国連障害者権利条約の批准のための必須法と考えられていたため、わが国においても鋭意法制化されたものです。
法律成立後施行までの2年10ヶ月はいわば諸般の準備の期間で、27年度がその最終局面です。
障害者団体などは「障害者差別禁止法」という名称での法律化を求めていましたが、「禁止」という厳しい文言への国の躊躇や、先に改正された「改正障害者基本法」における表現に則り、法律案の段階で「解消法」とされたようです。
すでに法に基づく政府としての基本方針が閣議決定され、現在その基本方針に即した対応要領(行政府機関などの職員が適切に対応するための必要な要綱)、対応指針(民間の事業所―法人であって個人ではない―が配慮すべきガイドライン)の作成が進捗しています。
本法の主旨は、もちろん障害のある人たちへのさまざまな差別をなくしてゆくことですが、具体的には、障害のある人たちへの「他の者との平等を基礎として」、「障害を理由とした不当な差別的取扱いを禁止し」、又、「合理的配慮を提供しないことも差別である」として、そのための対応を義務として、あるいは努力義務として行政機関や民間の事業者などに求めることにあります。
しかし、いずれの義務違反に対しても、今のところは行政上の助言、指導や勧告措置にとどまり、いわゆる「罰則」の規定はもうけられていません。
いずれにしても今年度には法制度の運用に関する詳細がとり決められます。本法がまさに期待通りの実効ある役割を担えるよう、今後発出される報知内容に耳目をこらす必要があります。
ちなみに、国の動きとは別に、全国の各自治体では独自な障害者差別禁止の条例づくりが進んでいます。様々な名称の条例で、すでに14道府県市に及びます。大阪府においても現在検討されているようです。
以上、主要な社会福祉(障害者福祉)の近況について述べましたが、他にも看過できない事態は多数です。例えば、高齢者福祉の特別養護老人ホームの利用にまつわる制度運用の改悪です。又、要支援者への制度実施責任主体や支援のあり方などをめぐる後退です。
あげれば、枚挙にいとまがありません。本当に、この国の社会福祉は、そして障害者福祉はどこまで厳しくなり、人に冷たくなってゆくのでしょうか。
【文責 吉川喜章】