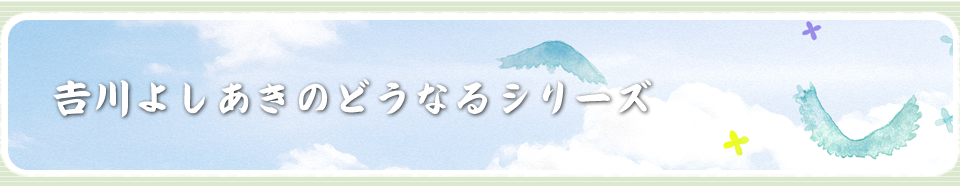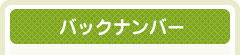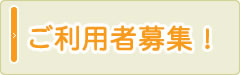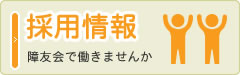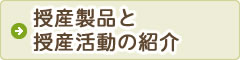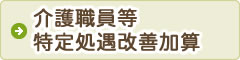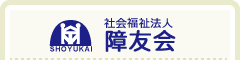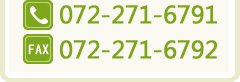どうなるこの国の障害者福祉
社会福祉を商売にしていいのか
※至心2014年7月号に関しましては、どうなるこの国の障害者福祉が休載となっており、ホームページ上への掲載もありません。ご了承ください。
この10余年の間に、わが国の障害者福祉は大きく変貌しました。そのありようは過激といって過言ではありません。
平成12年度、高齢者福祉施策への介護保険制度の導入を端緒に、以降年次的な進捗を経て、今日ではほぼすべての社会福祉領域に及んでいます。
それは、これまでの社会福祉の理念やあり方、仕組みとは全く「別次元」の施策への転換でした。
近年の、わが国の経済の低迷や税収不足などによる国家財政の窮迫、それと並行するような少子高齢化による急激な人口構造の変化。これらの諸要因がわが国の社会福祉の見直しをうながしたとされてはいますが、国は他にもいくつかの理由を主張しています。
「今日、社会福祉の対象はかつての『一部の人たち』ではない。多様なニーズをかかえる国民全体に拡大している。その意味でも今までの社会福祉のありようでは対応できない。措置制度では国民の基礎的な権利性は保障しえても、拡大多様化した国民ひとり一人の価値観やニーズにはとても応えることができない。措置制度はすでに時代状況に適合せず、又、国際的な潮流にももとるもの。云々」と。
ともあれ、第2次世界大戦後に鋭意構築され、以来50余年にわたって間断なく保持継承されてきたわが国の社会福祉の形は、この10余年の間に大きく変質しました。
その最大の特徴は、いわば社会福祉の「商業化」です。
わが国の社会福祉の基本的な位置づけである「国民の権利と国の責務―憲法第25条」という関係性が著しく変質し、「国民の自己責任によるサービスの購入」という市場原理的な契約関係に成り変ったことです。
国民の権利として原則無償であった社会福祉は、原則有償の「福祉サービスの購入」というあり方と費用負担の仕組みに変わりました。
国や地方自治体などの「公」と公の支配に属しつつ公の責務を代行する特別な公益法人―社会福祉法人(国の許可による)だけが実施できた社会福祉の実施が、この間の法制度改変によっていわゆる営利法人(株式会社や有限会社)にも開放されました。国は多様で多数の実施者の参入を呼んで大幅な社会福祉基盤の拡大整備を図りましたが、この営利法人の参入がわが国の社会福祉を一気に「商業化」にむかわせました。社会福祉が「投資」の対象にされ、「儲かる(?)」事業にされました。そのためにか、社会福祉の本来のあり方にそぐわない、理念なき不適切な事態が種々の社会福祉現場で散見されるようになりました。
かつては社会福祉には全く無縁であった法制度上の様々な言葉(表現など)も変化の一途です。それらはいわば「経済用語」におきかえられて、すでに普通に、日常的に使用されるようになってきています。
社会福祉の諸制度や支援策が「福祉サービス」と総称され、その利用者は「受益者」や「消費者」。社会福祉の実施に要する費用で、実施者が求めて国が拠出する経費を「報酬」。その収支差は「利益」とまで表現されるようになってきています。さらに、実施者の将来への備えなどであるべき「利益」の累積保有金を「内部保留金」。事業の運営を「営業」。実施者は「業界での生き残り」をかけた「営業努力」が必要、とさえ言われるようにもなってきました。
そして、最近の社会福祉法人への「課税」の議論です。社会福祉の「商業化」の究極のあらわれと言うほかありません。
公の責務を公に代って実施してきたからこその「非課税」扱いであったはずです。それが諸方からの圧力(?)でいつの間にか「優遇措置」と決めつけられるようになりました。
はたして、何と比べての「優遇措置」なのでしょうか。もはや言わずもがなです。あらたに社会福祉に参入し実施者となった営利法人に比較してです。
社会福祉法人への課税はつまりは社会福祉事業への課税です。本来、公の責務による公の施策、事業であるべき社会福祉のへの課税は、まさに国自らが社会福祉の公的性を否定することです。社会福祉をひとつの「経済分野」とみなし、社会福祉の実施―事業―を「経済活動」と位置づけた結果です。イコールフィッティングのためとして営利法人を同等の条件―社会福祉法人への課税―を社会福祉法人に課すことは、結局は国の責任を自らが放棄すること、と言わねばなりません。
わが国の社会福祉の大変身は、今日このような段階にまで至りました。そしてその動向はいまだとどまるところを知りません。
国が強調する国の財政のひっ迫や急速な少子高齢化問題は確かに喫緊の重要な政策課題です。そのための10余年に及ぶ社会保障・社会福祉基礎構造改革であったのでしょう。
とはいえ、社会福祉をこのまま「商業化」の大波にさらしつづけていてよいものでしょうか。今、わが国に展開する現状はある意味では国の思惑のとおりであったかもしれません。しかし、その結果はきわめて重大かつ深刻です。
何よりも憲法で保障された国民の社会福祉に対する権利性が大きく損なわれつつあります。同時に、憲法が求める国の責務も著しく後退しつづけています。障害者福祉に関しては「障害者権利条約」との整合性さえ問われる事態です。
昔も今も、そしてこれからも、社会福祉は国民のいのちや暮しに発現する様々な社会的課題に対応する公的で社会的な施策、事業です。そこに「商売」の立ち入る余地はありません。又、そうでなくてはならないのです。
今こそ、日本国憲法第25条の精神、理念に誰もがたち戻るべきときです。
社会福祉の本来の姿への、「再度の転換」を強く訴えます。
国の責任はきわめて重大です。